
 古代ローマは王政から共和制を経て帝政へと政治形態を変化させながら古代ギリシアとは違った豊かな文化を形成し、のちのヨーロッパに多大な精神的遺産を残しました。しかし、この古代ローマの文化およびそれを土壌とする古代ローマの文学を理解しようとするならば、やはり古代ローマの歴史を概観する必要があるでしょう。とはいえ「ローマは一日して成らず」です。その歴史には紀元前約750年から始まる1200年以上の歴史があります。まずはその激動の歴史と豊穣な文化を概観していきましょう。
古代ローマは王政から共和制を経て帝政へと政治形態を変化させながら古代ギリシアとは違った豊かな文化を形成し、のちのヨーロッパに多大な精神的遺産を残しました。しかし、この古代ローマの文化およびそれを土壌とする古代ローマの文学を理解しようとするならば、やはり古代ローマの歴史を概観する必要があるでしょう。とはいえ「ローマは一日して成らず」です。その歴史には紀元前約750年から始まる1200年以上の歴史があります。まずはその激動の歴史と豊穣な文化を概観していきましょう。
【古代ローマの歴史について】
古代ローマと呼ばれる時代は、歴史家によって多少のズレはありますが、おおよそ紀元前753年から紀元後476年までの期間を指します。この約1200年のあいだにローマは政治体制が王政、共和制、帝政と変化していきました。今回はそれぞれの政治体制に沿ってローマの歴史を概観していきましょう。
 【ローマ建国神話について】
【ローマ建国神話について】
王政期のローマは一般に王政ローマと呼ばれ、ローマ建国とされる紀元前753年から紀元前509年までの期間を指します。古代ギリシアが集落・部族間の貿易を通して緩やかに各ポリスを形成していったのとは異なり、古代ローマには建国神話と呼ばれるものが存在します。この古代ローマ建国神話には古代ギリシアのトロイア戦争が関係しています。
トロイア戦争は、小アジアに位置するトロイアの王子パリスがスパルタ王メネラオスの妃ヘレネーを攫ったことに端を発する、イーリオス勢(トロイア軍)とアカイア勢(ギリシア連合軍)のあいだの戦争です。アキレウスの奮闘やオデュッセウスの知略もあって、この戦争でトロイア王プリアモスをはじめとして王子ヘクトール、パリスら王家の人間はみな命を落とし、トロイア王家は滅亡しました。
しかし、トロイア王家傍系にあったある将だけは辛うじて生き残ることができました。この将こそがアエネーアース、本ガイド「ラテン叙事詩」の項で扱うウェルギリウスによる叙事詩『アエネーイス』の主人公です。アエネーアースの物語は『アエネーイス』を扱う際に詳細にお話ししますので、ここでは簡潔に説明します。
火が放たれたトロイアから命からがら家族とともに逃げ延びたアエネーアースは、アポロン神の「祖先の地を目指せ」という託宣を受けて、トロイアの避難民とともにイタリア半島のラティウムに到着します。ここにラウィニウムという都市を築き、ラティウムの王となりました(名前がややこしい!)。
さて、ここでお気付きの方もいらっしゃると思いますが、アエネーアースが築いたのはラウィニウムであってローマではありません。では誰がローマを建国したのでしょうか。それはアエネーアースの子孫ロームルスです。ここからはロームルスの物語をお話しします。なかなか王政ローマがどのようなものであったかの説明に行き着きませんが、どうかお急ぎにならないように。「ローマは一日にして成らず」です。
 ラティウムの王はアルバ・ロンガと呼ばれる地に王宮を構えていたことからアルバ王と呼ばれていました(これもまたややこしい!)。時代はアエネーアースから12代下ります。この時代、アルバ王家に内乱が起きました。13代目のアルバ王プロカが死ぬと、その長男ヌミトルが王位を継ぎ、次男アムーリウスはトロイア王家時代から引き継がれてきた財宝を王位の代わりに手にします。しかし、財宝があってもやはり王位がなければ満足しなかったのでしょう。アムーリウスはその財力を使ってヌミトルを王位から追放し、自らがアルバ王になります。
ラティウムの王はアルバ・ロンガと呼ばれる地に王宮を構えていたことからアルバ王と呼ばれていました(これもまたややこしい!)。時代はアエネーアースから12代下ります。この時代、アルバ王家に内乱が起きました。13代目のアルバ王プロカが死ぬと、その長男ヌミトルが王位を継ぎ、次男アムーリウスはトロイア王家時代から引き継がれてきた財宝を王位の代わりに手にします。しかし、財宝があってもやはり王位がなければ満足しなかったのでしょう。アムーリウスはその財力を使ってヌミトルを王位から追放し、自らがアルバ王になります。
アムーリウスは流石に兄であるヌミトルを殺しまではしなかったものの、その血脈を断絶させんとして、ヌミトルの息子を強盗にやられたように装って殺し、娘のレアを女神ウェスタ(ギリシア神話における火床の神ヘスティア)の巫女にさせます。というのも、神殿の巫女というのは神に身体を捧げる存在であり、それゆえに婚姻は許されていませんでした。さて、巫女としていわば神殿内に軟禁されたレアですが、彼女のもとにやって来た軍神マース(ギリシア神話におけるアレース神)に見初められ、神であるマースに身体を捧げ、ロームルスとレムスの双子を授かります。しかし、こうなると困るのがヌミトルの血脈を断とうとしたアムーリウスです。彼はレアが双子を産んだと知るや否や、王位を継ぎ得る双子を殺すよう兵士に命じます。しかし、罪のない赤子を殺せる者がおりましょうか。兵士は双子を憐れんで、ひそかに彼らを籠に入れてテヴェレ川に流しました。良き人に拾われることを願って。
ロームルスとレムスの二人はテヴェレ川の森に住む雌狼に救い上げられ、彼らは狼の乳によって養われます。やがて、羊飼いのファウストゥルスが双子を見つけ、妻とともに彼らを立派な成人になるまで育てます。さてある時、羊飼いになっていたレムスは祖父であるヌミトル配下の羊飼いと牧草地を巡って諍いを起こし、アルバの宮廷に連行されてしまいます。アルバ王であるアムーリウスはレムスに裁きを下し、刑の執行を当事者であるヌミトルに任せます。こうしてレムスは祖父とは知らずにヌミトルのもとへと向かうことになりました。
さて、驚いたのはロームルスでした。彼は所用で家を空けていたのですが、戻ってきて事の顛末を聞くと、すぐさま武装して弟を助け出そうと気負います。ですが、育ての親ファウストゥルスが彼を止めます。彼は双子の出自を知っており、そのことを今まで二人に黙っていました。というのも、まだ一人前になる前にこの秘密を知ったなら、彼らがアムーリウスを倒そうと無茶をすることは目に見えていたからです。しかし、実の祖父と孫が知らず知らずのうちに敵対しているのですから、今やもう黙っている訳にはいきません。彼は今まで秘密にしていた彼ら双子の出自をロームルスに打ち明けます。倒すべき本当の敵はアムーリウスだと知ったロームルスは一旦レムス救出を取り止めました。というのも、アルバ王であるアムーリウスを倒すにはこちらも相当の兵力が必要だと考えたからです。
一方、ヌミトルのもとへと連れていかれたレムスも自らの出自を知ることになります。レムスを連行していたヌミトルは若者のその堂々たる風貌と落ち着いた態度に感心し、家に着くなり人払いをし、彼に素性を述べるよう促します。すると、祖父であるヌミトルはこの若者は自分の孫ではないかと思い至り、二人は対話のなかで互いが実の祖父と孫の関係であることを知ります。実の孫と再会したヌミトルはレムスを解放し、彼にアムーリウスの非道を語って復讐を説きます。
さて、解放されたレムスはロームルスと合流し、双子はさっそく祖父と共にアムーリウス打倒に向けて動き出します。ヌミトルは王位を簒奪されたとしても、やはり正統な王であり、彼に対して為されたアムーリウスの非道を知るゆえにヌミトルを支持する者は少なくありません。アムーリウス打倒の支持者を集めたヌミトルと孫の二人は、一族郎党を率いて支持者と共にアルバの宮廷へ攻め入ります。宮廷を固めていたのは少数の重装兵のみでした。それに対して、こちらはヌミトルの一族郎党とアムーリウス王を憎む民衆たち、そしてロームルスとレムスです。彼らは易々とアムーリウスを斃し、復讐を遂げました。
 さて、復権を果たしたヌミトルはロームルスとレムスをアルバ王子として正式に認めますが、彼らは祖父の引き留めにも拘わらず、新しい王国を建設するためにアルバを離れます。というのも、彼らにとってアルバはあくまで異国の地、赤子のときに拾われ、育てられたテヴェレ川近郊こそが彼らの故郷でした。双子は新たな王国をこのテヴェレの地に建設することを決意しました。
さて、復権を果たしたヌミトルはロームルスとレムスをアルバ王子として正式に認めますが、彼らは祖父の引き留めにも拘わらず、新しい王国を建設するためにアルバを離れます。というのも、彼らにとってアルバはあくまで異国の地、赤子のときに拾われ、育てられたテヴェレ川近郊こそが彼らの故郷でした。双子は新たな王国をこのテヴェレの地に建設することを決意しました。
しかし、王位を継ぐ双子は反目しあう運命にあるのでしょうか、彼らは統治者を巡って対立し、兄弟仲は次第に険悪になっていきます。とりあえずは分割統治ということになりましたが、やがてレムスが国境を侵害するようになり、兄弟間の関係は決裂してしまいます。結局二人は統治者を巡って決闘することになり、壮絶な殺し合いの結果、ロームルスがレムスに勝利しました。ここにロームルス王が誕生し、彼は自らが建国した王国を「ローマ」と名付けました。
(画像1枚目:フェデリコ・バロッチ『炎上するトロイアから脱出するアエネーアース』1598年)
(画像2枚目:ペーター・パウル・ルーベンス『ロームルスとレムス』1616年)
(画像3枚目:作者不明『ロームルスとレムス』)
 【王政ローマの政治体制】
【王政ローマの政治体制】
以上がローマ建国神話になります。もちろん、神話ですので語り手によって様々なヴァリエーションがありますし、考古学的に不確かな点は多々あるでしょう。しかし、ロームルスが作ったとされる諸制度は政治体制が変わっていくなかでもローマという国家の根本であり続けました。それが国政の三権分立です。王政ローマの場合、国政は王と元老院、そして民会が分担しました。すなわち、統治者として王が君臨しつつも、元老院と民会が王権を制御していたのです。
元老院とは王の助言機関で、パトリキと呼ばれる貴族の長老たちが有力者として王の政策にアドバイスや忠告、場合によっては王を諫めることで王の暴走を防止していました。元老院が有力貴族によって構成される議会である一方、民会は文字通りローマ市民によって構成される議会でした。今日の議会とは異なり、法を定める立法の機能こそ持っていませんでしたが、王が何かしらの政策を行う際には必ず民会に賛否を問わなければなりませんでした。また、民会は王の選定も担っていました。ローマの王は終身制ではありましたが、他国とは違い、血統によって自動的に王になるのではありません。しかも、ローマ市民ではない人物もローマ王になることすらできました。実際、ロームルスの死後、二代目ローマ王に選ばれたのはローマ市民でも、ラテン人でもない、ロームルスの時代にローマと一時期戦争をしていたザビーニ人のヌマ・ポンピリウスです。また、ローマを建国した王のロームルスですら、治世の途中で民会の選挙に出馬し、改めて王として選出されています。
このように、王政ローマは王と貴族、市民が一体となって国政を進めていき、その領土を拡大し産業を発展させていきました。しかし、権力者とは更なる権力を欲するものです。第七代目のローマ王タルクィニウス・スペルブスはロームルスの作り上げた三権分立の制度を破壊し、王の独裁を目論みました。のちに「傲慢王」と呼ばれることになるこの王は、元老院と民会とを問わず先王を支持していた議員を全員殺し、民会の選出も、元老院の承認もなく王に即位したのです。その後もタルクィニウスは元老院に助言を乞うことも、民会に賛否を問うこともなく自らの意志のみで政策を決定していきました。当然、三権分立を伝統としてきたローマの市民たちは怒りを爆発させます。有力貴族の一人であり、のちに共和制ローマの初代執政官となるルキウス・ユニウス・ブルトゥスが王一族の追放を訴える演説をし、市民もそれに従って、遂にはタルクィニウス一族はローマから追放されます。紀元前509年、ここにローマの王政は終焉を迎えることになりました。
【共和制ローマの政治体制】
 さて、王を追放したローマは新たに王を立てることをしませんでした。その代わり、従来の元老院と民会に政務官と呼ばれるいわば国会議員兼官僚を加えた新たな民主政体、すなわち、王や君主ではなく市民が主権を持つ共和制へと移ります。単に「傲慢王」タルクィニウス個人の悪政だけであったなら、新たに王を立てることも選択肢のうちにあったはずです。しかし、ローマ人は王による独裁を嫌って、建国より続く王政という伝統を捨ててでも、共和制という新たな政治体制を選びました。
さて、王を追放したローマは新たに王を立てることをしませんでした。その代わり、従来の元老院と民会に政務官と呼ばれるいわば国会議員兼官僚を加えた新たな民主政体、すなわち、王や君主ではなく市民が主権を持つ共和制へと移ります。単に「傲慢王」タルクィニウス個人の悪政だけであったなら、新たに王を立てることも選択肢のうちにあったはずです。しかし、ローマ人は王による独裁を嫌って、建国より続く王政という伝統を捨ててでも、共和制という新たな政治体制を選びました。
では、なぜローマ人はそれほどまでに王による独裁を嫌ったのでしょうか。確かにローマ人が捨てた王政という政治体制は、ローマ建国以来の伝統でした。しかし、それは彼らにとって伝統の表層的な部分でしかなかったのかもしれません。建国以来続くローマの伝統の本質的な部分、恐らくそれは建国者ロームルスが作った三権分立の制度、いやそれよりも、この三権分立によって生み出された「自由なローマ市民」という概念だったのでしょう。実際、共和制ローマ以降、のちに共和制から帝政に移ってもなお使われ続けたローマの国章には、次のような略号が刻まれています。すなわち、「S・P・Q・R」と。これは「Senatus Populusque Romanus」(セナートゥス・ポプルスクェ・ロマーヌス)の略号で、直訳すれば「ローマの元老院と市民たち」という意味になります。政治体制が共和制から帝政に移っても、この「S・P・Q・R」に皇帝を意味する「Imperator」の頭文字「I」が入ることはありませんでした。それほどにまでローマ人は自由であることを大事にし、自らの誇りとしたのでした。彼らにとって自らの自由こそが最重要であり、それを存立させるためなら三権分立のうち、行政権が「王」にあろうと「政務官」にあろうと同じことなのです。それゆえ、彼らローマ人は王政を捨てて共和制という新たな政治体制を選んだのでした。
共和制ローマでは、王政ローマにおいて王が民会の選挙によって選ばれたのと同じように、政務官は民会の選挙によって選ばれました。この政務官は一年の任期限りで、連続して同じ人物が政務官に選ばれることは出来ません。また、彼ら政務官には「法務官」や「財務官」などの様々な役職がありましたが、そのなかでも国政および軍事の最高責任者は「執政官」と呼ばれていました。現代の首相に近い立ち位置にあるこの執政官が王政ローマの王に代わり、共和制ローマにおいては行政権を統括していました。この執政官ももちろん、他の政務官と同じく一年限りの任期でした。しかし、王政ローマにおける王や現代の首相と異なる点はそれだけではありません。共和制ローマの政治体制で最も特徴的な点は、執政官に2名の人物が選出されていたという点でしょう。つまり、国家元首たる執政官を2名選出し、互いに牽制し監視しあうことで独裁を防ごうとしているのです。ここにも、やはりローマ人の「独裁嫌い」が表れています。
(画像:『A modern recreation of a Roman standard』)
【共和制ローマと戦争】
 さて、ここまで共和制ローマの政治体制についてローマ人の文化とともにお話してきましたが、次に共和制ローマの具体的な歴史の方に分け入っていきましょう。共和制ローマの時代は戦争の時代だったと言えるでしょう(王政期ローマも戦争が多かったのですが)。外敵との戦い、領土拡張、内戦と共和制ローマは戦いに明け暮れました。その中でも有名なのはアフリカ大陸北岸の地中海地域に繫栄した国カルタゴの将軍ハンニバルと、ローマの執政官スキピオ・アフリカヌスが戦った第二次ポエニ戦争、特にカンナエの戦いでしょう。彼ら二人のライバル関係はしばしば小説や漫画の題材になっていますし、その戦術・戦略も未だに現代の教本に載るほどの見事なものでした。しかし、紙面が限られている以上、本ガイドでは惜しみつつも参考文献を挙げるのみにして、共和制ローマでは凡そどのような戦争が行われ、どのような結果がもたらされたかだけに留めおきます。
さて、ここまで共和制ローマの政治体制についてローマ人の文化とともにお話してきましたが、次に共和制ローマの具体的な歴史の方に分け入っていきましょう。共和制ローマの時代は戦争の時代だったと言えるでしょう(王政期ローマも戦争が多かったのですが)。外敵との戦い、領土拡張、内戦と共和制ローマは戦いに明け暮れました。その中でも有名なのはアフリカ大陸北岸の地中海地域に繫栄した国カルタゴの将軍ハンニバルと、ローマの執政官スキピオ・アフリカヌスが戦った第二次ポエニ戦争、特にカンナエの戦いでしょう。彼ら二人のライバル関係はしばしば小説や漫画の題材になっていますし、その戦術・戦略も未だに現代の教本に載るほどの見事なものでした。しかし、紙面が限られている以上、本ガイドでは惜しみつつも参考文献を挙げるのみにして、共和制ローマでは凡そどのような戦争が行われ、どのような結果がもたらされたかだけに留めおきます。
共和制ローマの最初の戦争は周辺諸都市との戦争でした。この戦争は対外戦争ですが、その勃発にはローマの内政も関係しています。共和制ローマの元老院選挙被選挙権は40歳以上の市民にのみ与えられていました。現在の基準で考えてもとんでもないことですが、当時の平均寿命を考えるならばもっととんでもないことになります。というのも、研究によって多少の変化はありますが、当時のローマ人の平均寿命はおおよそ男性は30歳、女性はもっと短く25歳程度だからです。要するにかなりの老人しか被選挙権を得られなかったわけです。また、古代は十分に医療が発達しておらず、医療を受けるということ自体難しいことでした。そのため、40歳以上生きられるローマ人とは、十分な食事や快適な住まい、医療行為を受けられる金銭などを持つ権力者のことでしかありません。これに初代執政官ルキウス・ユニウス・ブルトゥスの息子ティトゥスを中心に若いローマ市民たちが反対し、王政復古を企みました。この企てはブルトゥスが息子ティトゥスをはじめとする首謀者たちを処刑することで鎮圧されますが、これをきっかけとして、共和制ローマはかつて同盟していたエトルリア(イタリア半島中部)諸都市と決定的に対立することになります。というのも、エトルリア諸都市はあくまでローマ王と同盟していたからです。エトルリア諸都市としては王を追放し、また王政復古の動きを力で潰した共和制ローマともはや同盟を組む道理はないわけです。さらに、追放されたローマ王タルクィニウスはエトルリア人で、追放されたのちはエトルリアに亡命していました。彼はローマでの王政復古の動きが失敗したことを知ると、エトルリア諸都市から兵を借りてローマを攻めました。これが共和制ローマ最初の戦争です。ローマはエトルリア諸都市に比べて新興都市であり技術も劣っていました。戦争勃発によってエトルリアが去ったローマは国力が大きく低下し、また初代執政官ブルトゥスが戦闘で先王タルクィニウスの息子の一人と刺し違えになるなどによって、ローマは次第に追い詰められていき遂には市を包囲されるに至ります。しかし、タルクィニウスがどれだけ攻めてもローマは負けを認めません。やはりここにもローマ人の「独裁嫌い」が強く反映されているのでしょう。結局、タルクィニウスは根負けして犠牲の割に得るものが少ないと判断し、共和制ローマと和平を結びます。戦争によって拡張していったというローマのイメージに反して意外にも共和制ローマの最初の戦争はほとんど敗戦と言っていいものでした。
さて、エトルリア諸都市との和平を果たした共和制ローマでしたが、間もなく紀元前4世紀から次なる脅威にさらされることになります。というのもアルプスの北側、ローマが「ガリア」と呼んでいた地域(現在のフランスやオランダ、ドイツなどから成る一帯)からケルト人(ガリア人)がアルプス山脈を越えて侵入してきたのです。
ケルト人のセノネス族との戦いでセノネス族に攻め込まれ、ローマは中心部であるカンピドリオ以外の全ての市内でセノネス族に略奪・破壊されることになります。しかし、セノネス族側も伝染病によってローマの包囲が難しくなり、ローマとの停戦協定を結ぶことにしました。ローマ側が大量の金を支払うことで停戦協定は合意に至ります。その際、セノネス族は通常より重い重りで金を量らせようとしました。ローマ側にそのことが発覚すると、セノネス族の首長は自分のベルトと剣を秤の重り側に投げかけ、「征服された者に災いあれ」と言い放ちます。しかし、まさにそのとき、ローマの名将マルクス・フリウス・カミルスが部隊と共に到着したのです。彼は約10年前にローマ軍を指揮してウェイイというエルトリアの街を攻略したのですが、この都市に遷都しようとしたローマ市民に異を唱え、その異議に反感を持った市民たちによって半ば追放されるような形でローマを去っていました。カミルスは剣を秤のもう一方に置いて「金ではなく、鉄こそが祖国を回復させる」と応え、ガリア側への攻撃を開始しました。カミルスは見事セノネス族の軍に勝利し、市民は彼を「第二のロームルス」と呼んで歓呼しました。
さて、これらの戦争は共和制ローマの政治体制に大きな影響を与えることになりました。それまではローマの政治において貴族が大きな発言力を持っていたのですが、戦争において主体となって戦った市民が徐々にその政治的発言力を獲得するようになりました。結果、市民の権利を擁護する「護民官」が設置され、国政の最高責任者である執政官二人のうち一人は必ず市民から選出されることが定められました。また、それまで法の制定には元老院の承認が必須でしたが、元老院の承認なしで民会の決定が法になることが定められます。
 このように市民がより一層の力を得たローマはその後、イタリア半島を統一するに至ります。戦争によって政治的発言力を得た市民たちを中心として繁栄を誇った共和制ローマでしたが、しかし戦争によってまた共和制が崩壊することになります。そのきっかけとなったのは、アフリカ大陸北岸において地中海貿易によって栄えたフェニキア人国家カルタゴとの地中海の覇権を巡る戦争ーーポエニ戦争です(ポエニはラテン語でフェニキア人を指します)。
このように市民がより一層の力を得たローマはその後、イタリア半島を統一するに至ります。戦争によって政治的発言力を得た市民たちを中心として繁栄を誇った共和制ローマでしたが、しかし戦争によってまた共和制が崩壊することになります。そのきっかけとなったのは、アフリカ大陸北岸において地中海貿易によって栄えたフェニキア人国家カルタゴとの地中海の覇権を巡る戦争ーーポエニ戦争です(ポエニはラテン語でフェニキア人を指します)。
発端となったのは、イタリア半島のすぐ南に位置するシチリア島でした。この経緯はややこしい事この上ないので省きますが、シチリアの覇権を賭けてローマとカルタゴは戦うことになります。一時はカルタゴの将軍ハミルカル・バルカがシチリア島のほぼ全土を掌握します。しかし、ローマは諦めていませんでした。勝利を確定的と考えたカルタゴ本国が海軍を縮小したのをローマは好機と捉え、壊滅していた艦隊を再建、シチリア島西部のアエガテス諸島の海戦で決定的な勝利を得ます。これによって、制海権を抑えられたシチリア島のバルカ将軍率いるカルタゴ軍は補給を受けることができず、ローマに降伏したのでした。シチリア島を巡る戦いを第一次ポエニ戦争(紀元前264~241年)と言います。
※第一次ポエニ戦争から約30年後に勃発する第二次ポエニ戦争、特にバルカ将軍の息子で「雷将」と呼ばれたハンニバル将軍とローマの戦いはあまりにも「熱い」ため、このガイドでは敢えて扱いません。というか扱えません。その代わりにこの「熱い」第二次ポエニ戦争をわかりやすく、また詳細に解説しているYouTube動画を紹介します:『ハンニバル戦記』「非株式会社いつかやる」 様 より。
(画像1枚目:フランチェスコ・デ・ロッシ『カミッルスの凱旋式』1545年)
(画像2枚目:ハインリヒ・ロイテマン『アルプス山脈を越えるハンニバルの軍』1886年)
【属州の獲得と共和制の崩壊】
 この第一次ポエニ戦争に勝利したローマはシチリア島を初めて属州とします。属州とは端的に言えばローマ本国以外の領土のことです。第一次ポエニ戦争までのローマはイタリア半島において他のエルトリア諸都市と戦争をしていったわけですが、ローマはイタリア半島を統一する際、これらの諸都市を征服するのではなく、これらの諸都市と同盟を結ぶことで統一していきました。つまり、「ローマ」は都市国家ローマと諸都市国家の連合体です。これに対して、ローマが「征服」し「支配」した領土のことを「属州」と言います。
この第一次ポエニ戦争に勝利したローマはシチリア島を初めて属州とします。属州とは端的に言えばローマ本国以外の領土のことです。第一次ポエニ戦争までのローマはイタリア半島において他のエルトリア諸都市と戦争をしていったわけですが、ローマはイタリア半島を統一する際、これらの諸都市を征服するのではなく、これらの諸都市と同盟を結ぶことで統一していきました。つまり、「ローマ」は都市国家ローマと諸都市国家の連合体です。これに対して、ローマが「征服」し「支配」した領土のことを「属州」と言います。
ローマはポエニ戦争(第二次ポエニ戦争:紀元前219年~201年、第三次ポエニ戦争:紀元前149年~146年)を通じて、イタリア半島西部に位置するサルディーニャ島およびコルシカ島、現在のスペイン・ポルトガルにあたるヒスパニア、アフリカ北岸地域(カルタゴ)を属州として獲得することになります。これら属州に赴任したローマの総督は現地民に対して多くの税金を課し、属州から収奪した莫大な冨と安価な農作物は急増するローマの人口とローマの繁栄を支えることになります。
しかし、一方で属州からの安価な農作物はローマにおける共和制の崩壊の大きな要因ともなりました。というのもイタリア半島、つまりローマ本国の自作農民はこの安価な農作物の流入によって生活が立ち行かなくなり、没落していったからです。結果、共和制ローマの政情は不安定化し、内乱が立て続けに起きることになります。
また、ローマ本国における自作農民の没落は政治における軍人の台頭を許し、共和制崩壊の直接的な原因の一つになります。というのも、ローマ軍の中心は自作農民からなる市民だったからです。ローマは続発する内乱や引き続き行われる対外戦争ゆえに、自作農民の没落によって弱体化した軍を縮小することはできません。それゆえ、軍の改革と軍の指揮能力に優れた執政官を選ぶ必要が生じます。結果、それまで市民を中心に構成していたローマ軍に志願兵制度が導入され、多くは貧民からなる志願兵たちは司令官の私兵と化していきます。
このような状況の中で台頭してきた人物が皇帝を意味する「カイザー(Kaiser)」や「ツァーリ(царь)」の語源となったガイウス・ユリウス・カエサル、その人です。彼は、上記の軍事改革を断行した平民出身の英雄ガイウス・マリウス(大マリウス)の義弟ガイウス・ユリウス・カエサルの子として、父親と同じ名前を付けられて生まれました。マリウスと対立し、対立に勝利して独裁官(国家の非常事態に選出されて、ローマの全権を一人で担う政務官)になったコルネリウス・スッラが死去すると、カエサルは元老院に不満を持つ政務官グナエウス・ポンペイウスと結んで執政官になり、スッラ派の重鎮マルクス・リキニウス・クラッススとともに「三頭政治」と呼ばれる寡頭政治を展開しました。
執政官としての任期を終えたカエサルは、この三頭政治の期間中にガリア地方へと侵攻し、ついには現在のイギリス南部にあたるブリタンニアまでのガリアを征服してローマの属州としました。このガリア戦争の経験を書いたものが有名な『ガリア戦記』です。ガリア戦争でカエサルは一挙に名声と力を高めましたが、その一方で元老院の警戒心を強めました。
古代イランのパルティア王朝へと遠征していたクラッススがカルラエの戦いで戦死すると、三頭政治は瓦解し、カエサルとポンペイウスは対立し始めます。元老院がカエサルの執政官への立候補を拒んだのをきっかけに、カエサルはガリアとローマ本国の境界にあたるルビコン川を渡ってローマに侵攻し、元老院と結んだポンペイウスとの内戦に突入します。内戦の結果、カエサルはポンペイウスに勝利し、プトレマイオス朝エジプトのアレクサンドリアへと逃れたポンペイウスは上陸の際に暗殺されました。
 追ってアレクサンドリアに到着したカエサルはファラオ(エジプト王)の座を巡って対立するクレオパトラ7世(かの有名なクレオパトラ)とその弟プトレマイオス13世の政争に介入します。もともとクレオパトラとプトレマイオス13世は先王である父プトレマイオス12世の遺言により共同でファラオの座に就いていましたが、クレオパトラは共同統治を嫌った弟によってアレクサンドリアを追放されていました。しかし、彼女はアレクサンドリアに到着したカエサルのもとを訪れ、彼に援助を申し出たのです。絨毯にくるまってカエサルのもとに忍び込むという有名なエピソードはこの時のことだそうです。クレオパトラに魅了されたカエサルは彼女の申し出に応じます。結果、カエサルとクレオパトラはナイルの戦いにおいてプトレマイオス13世に勝利し、クレオパトラともう一人の弟であるプトレマイオス14世が共同でファラオの座に就くことになりました。クレオパトラとプトレマイオス14世は夫婦でした。しかし、実際のところはクレオパトラはカエサルの愛人であり、属州化こそしませんでしたが、この政争介入によってプトレマイオス朝エジプトはローマの支配下に入りました。
追ってアレクサンドリアに到着したカエサルはファラオ(エジプト王)の座を巡って対立するクレオパトラ7世(かの有名なクレオパトラ)とその弟プトレマイオス13世の政争に介入します。もともとクレオパトラとプトレマイオス13世は先王である父プトレマイオス12世の遺言により共同でファラオの座に就いていましたが、クレオパトラは共同統治を嫌った弟によってアレクサンドリアを追放されていました。しかし、彼女はアレクサンドリアに到着したカエサルのもとを訪れ、彼に援助を申し出たのです。絨毯にくるまってカエサルのもとに忍び込むという有名なエピソードはこの時のことだそうです。クレオパトラに魅了されたカエサルは彼女の申し出に応じます。結果、カエサルとクレオパトラはナイルの戦いにおいてプトレマイオス13世に勝利し、クレオパトラともう一人の弟であるプトレマイオス14世が共同でファラオの座に就くことになりました。クレオパトラとプトレマイオス14世は夫婦でした。しかし、実際のところはクレオパトラはカエサルの愛人であり、属州化こそしませんでしたが、この政争介入によってプトレマイオス朝エジプトはローマの支配下に入りました。
ローマでの支配権を確立したカエサルは紀元前44年2月、終身独裁官に就任しました。これによって権力が一点に集中することになり、ローマの共和制は実質的に崩壊することになります。権力の頂点に立ったカエサルでしたが、王のように振舞う彼に対する反発も大きく、同年の3月15日、元老院へ出席した彼はブルトゥス(ブルータス)をはじめとする共和派の元老院議員によって暗殺されたのでした。

(画像1枚目:セバスティアン・スローツ『ユリウス・カエサル』1696年)
【共和制の終焉と帝政の開始】
 カエサルは暗殺されました。しかし、これは共和制の崩壊を止めるものではありませんでした。カエサル暗殺後、カエサル派によって再び三頭政治が行われることになります。第二回三頭政治を展開したのはカエサルの姪の息子であり、カエサルの遺言によって彼の後継者に選ばれたガイウス・オクタヴィアヌスとカエサル配下の名将マルクス・アントニウス、そしてカエサルの副官マルクス・レピドゥスです。彼らによってブルトゥスをはじめとする共和派は粛清されてしまいます。
カエサルは暗殺されました。しかし、これは共和制の崩壊を止めるものではありませんでした。カエサル暗殺後、カエサル派によって再び三頭政治が行われることになります。第二回三頭政治を展開したのはカエサルの姪の息子であり、カエサルの遺言によって彼の後継者に選ばれたガイウス・オクタヴィアヌスとカエサル配下の名将マルクス・アントニウス、そしてカエサルの副官マルクス・レピドゥスです。彼らによってブルトゥスをはじめとする共和派は粛清されてしまいます。
第二回三頭政治も長くは続きませんでした。共和派の粛清後、三頭はローマにおける支配地域を三分割することにしましたが、この三分割においてオクタヴィアヌスが不利になるよう分割されたために、オクタヴィアヌスとほかの二人(特にアントニウス)が対立するようになりました。シチリア島では、かつてカエサルとともに三頭政治の一角を担い、カエサルに敗れてアレクサンドリアで暗殺されたポンペイウスの遺児セクストゥスが第二回三頭政治に抵抗していましたが、三頭政治側はセクストゥスを打倒します。その際、レピドゥスがシチリア島の独占を目論みますが、これを好機と捉えたオクタヴィアヌスはレピドゥスの配下を買収することで失脚させます。その一方でオクタヴィアヌスはアントニウスの排除も画策します。アントニウスは古代イランのパルティア王朝への侵攻に失敗して名声と力を落としていました。彼は再起を図って、オクタヴィアヌスの姉であった妻と離縁して、以前から彼と親しく財力のあるクレオパトラと結婚します。オクタヴィアヌスは彼を弾劾しますが、彼はこの弾劾を拒絶するどころか彼とクレオパトラとの間に生まれた息子をファラオに据え、クレオパトラにエジプト女王の称号を授けました。オクタヴィアヌスは更にこれを利用して、元老院にローマのアントニウスおよびクレオパトラに対する宣戦布告を通告させます。オクタヴィアヌスは紀元前31年、アクティウムの海戦にてアントニウスに勝利、アレクサンドリアへと逃げ帰ったアントニウスとクレオパトラを追撃し、二人は自害しました。ここにプトレマイオス朝エジプトは滅亡しました。ローマに凱旋したオクタヴィアヌスは「元老院内の第一人者」を意味する「プリンケプス」の称号を贈られます。
さて、ローマの全権を握って頂点に立ったオクタヴィアヌスでしたが、全特権を返上し共和制への回帰を促す演説をします。オクタヴィアヌスは慎重でした。おそらくは、カエサルの暗殺を意識していたのでしょう。しかし、もはやオクタヴィアヌスに並ぶものはおらず、元老院の方が彼に国の全権を掌握するように何度も懇願します。オクタヴィアヌスは慎重にこの申し出を何度も断ったうえで、紀元前27年1月16日、これを承諾し、インペラトル・カエサル・アウグストゥスを名乗るようになりました(インペラトルは英語の「エンペラー」の語源で「無限の権を有する者」と言う意味、アウグストゥスは「尊厳者」という意味のラテン語)。初代ローマ皇帝アウグストゥスの誕生です。これにより、長らく続いた共和制ローマは終焉し、帝政が始まることになります。
(画像:製作者不明『プリマポルタのアウグストゥス』1863年発見)
【共和制のような帝政:元首制】
さて、オクタヴィアヌスが全権を握り、ローマ皇帝アウグストゥスとなることで始まったローマの帝政ですが、それは我々がイメージする一般的な「帝政」とは異なるものでした。我々がイメージする「帝政」は基本的に、絶対的な権力を持つ君主としての皇帝がいて、その皇帝を頂点として中央集権的な官僚国家が形成されている、といったものだと思います。確かにローマ帝国において皇帝はローマの全権を握る「インペラトル」でした。しかし、その一方で皇帝はあくまでも元老院およびローマ市民の「代表者」であり、実際、「暴君」として有名な第5代ローマ皇帝のネロは、皇帝だったにもかかわらず元老院から「国家の敵」と認定されて自害に追い込まれています。この「代表者」としての皇帝による帝政を「元首制」(プリンキパトゥス)と呼びます。
確かに王政ローマ以来の三権分立の伝統は政治的実態としてはなくなったかもしれません。しかし、少なくとも市民たちのローマという意識だけは帝政になっても強固に残り続けていたと言えるでしょう。帝政になっても、ローマの旗印たるSPQR=Senātus Populusque Rōmānus「ローマの元老院と市民」に「皇帝」を意味するImperatorのIは入らなかったのはその証左であると言えるかもしれません。
【パクス・ロマーナと五賢帝時代】
 初代ローマ皇帝となったオクタヴィアヌス、もといアウグストゥス帝はローマ帝国の軍事・政治の改革に着手しました。具体的には、常備軍の設置や通貨の整備、属州の元老院属州と皇帝属州への分割、国境を山脈や河川などの防衛のしやすい自然国境に定めるなどで、これによって帝国内の秩序は安定し、第3代皇帝カリグラや第5代皇帝ネロのような皇帝の暴政による一時的な荒廃はあれども、「パクス・ロマーナ」(ローマによる平和)と呼ばれる長らくの平和が続きました。
初代ローマ皇帝となったオクタヴィアヌス、もといアウグストゥス帝はローマ帝国の軍事・政治の改革に着手しました。具体的には、常備軍の設置や通貨の整備、属州の元老院属州と皇帝属州への分割、国境を山脈や河川などの防衛のしやすい自然国境に定めるなどで、これによって帝国内の秩序は安定し、第3代皇帝カリグラや第5代皇帝ネロのような皇帝の暴政による一時的な荒廃はあれども、「パクス・ロマーナ」(ローマによる平和)と呼ばれる長らくの平和が続きました。
また、紀元後1世紀末から2世紀までの、ネルウァ帝・トラヤヌス帝・ハドリアヌス帝・アントニヌス帝・アウレリウス帝の5人が治めた時代を五賢帝時代と呼びます(余談ですが、漫画『テルマエ・ロマエ』はこの五賢帝時代、ハドリアヌス帝統治下のローマが舞台となっています)。この時代にはヨーロッパ文明を特徴づける一大要素たるローマ法、「すべての道はローマに続く」と言われた交通網、その他度量衡や貨幣制度などの整備が行われ、ローマ帝国は最盛期を迎えました。また、五賢帝時代までのローマ皇帝は元老院とローマ市民の「代表者」であるにもかかわらず、実際には世襲によって即位していました。しかし、五賢帝時代のアウレリウス帝以外の皇帝は、彼らがローマ中から探し出した逸材を養子にして帝位を継がせるという形をとっており、実質的にも皇帝は元老院とローマ市民の「代表者」だったと言えるでしょう(実際、五賢帝の一人であるトラヤヌス帝は現在のスペイン・ポルトガルにあたるヒスパニア属州の出身でした)。最盛期を誇った五賢帝時代のローマ帝国は帝政とは言えども、名実ともに元首制の国家だったのです。
(画像:ミュンヘン・グリュプトテーク所蔵『トラヤヌス胸像』)
【帝政ローマの混乱と危機】
安定と繁栄を誇っていた五賢帝時代のローマでしたが、アウレリウス帝の息子で皇帝の座を継いだコンモドゥス帝の悪政と暗殺を皮切りに内乱が勃発し、ローマは次第に衰退していきます。内乱を制したのはカルタゴ人のセプティミウス・セウェルスで、彼が皇帝の座に就き、セウェルス朝が始まります。しかし、セウェルス朝においてもローマの政情は安定しませんでした。セウェルスの長男であるカラカラ帝は勅令(アントニヌス勅令)により全属州民にローマ市民権を与えます。これはローマ市民の義務とされていた相続税などの特別税の納税、兵役の義務を全属州民にも担わせ、税収増加と弱体化した軍の再生を狙ったものでした。そもそも、ローマ市民権は属州民にとって一種の特権であり、属州民がローマ市民権を獲得するためには補助兵として満期除隊までの25年間ローマ軍に勤務し続けなければなりませんでした。属州民はアントニヌス勅令によって突然ローマ市民権を与えられることになりました。しかし、これは裏を返せば一生をかけて目指すべき目標が失われたことになります。また他方、これはローマ市民にとっては自らの特権と誇りが失われたことを意味しました。結果的にアントニヌス勅令はカラカラ帝の思惑とは正反対の結果になり、ローマの国力は一挙に衰えることとなります。
235年、セウェルス朝5代目のローマ皇帝アレクサンデル・セウェルス帝が軍のクーデターにより暗殺されたことにより、セウェルス朝は断絶し、以降のローマは各地の軍の有力者が皇帝を僭称する軍人皇帝時代になります。なぜこのような事態になったのでしょうか。その原因は元首制、正確に言えば元首制の規定が不十分であったことにあります。というのも、ローマ皇帝は元老院とローマ市民の「代表者」であるという帝政初期からの元首制の制度において、ローマ皇帝の選出にあたっての明確な基準が存在していなかったのです。それゆえ、軍の推挙を受けた無数の軍人皇帝が乱立し、わずか50年のあいだに、元老院から承認(というより追認)された正式な皇帝だけでも21人、皇帝を僭称する者も含めると40人もの皇帝が即位するという事態になりました。そんな事態では政情が安定するわけもなく、ササン朝ペルシアやゲルマン民族といった外敵による侵攻が相次ぎ、ローマは未曽有の危機に陥ります。
【帝政ローマの分裂と崩壊】
 284年、皇帝に即位したディオクレティアヌスは、中央集権的官僚政治を徹底することで皇帝の権力を強化し、混乱をなんとか安定させようとします。これにより元老院とローマ市民の「代表者」としての皇帝という元首制は失われ、帝政ローマは専制君主制になっていきます。またディオクレティアヌスは「テトラルキア」と呼ばれる分割統治を導入します。これは不安定な政情のなか、広大になりすぎたローマの領地を治めるために行われた統治方法であり、共同皇帝制を用いて二人のローマ皇帝(東方正帝と西方正帝)が帝国を二分割統治し、そのうえでそれぞれの皇帝がそれぞれの領地を副帝と分割して統治するという四分割統治でした。
284年、皇帝に即位したディオクレティアヌスは、中央集権的官僚政治を徹底することで皇帝の権力を強化し、混乱をなんとか安定させようとします。これにより元老院とローマ市民の「代表者」としての皇帝という元首制は失われ、帝政ローマは専制君主制になっていきます。またディオクレティアヌスは「テトラルキア」と呼ばれる分割統治を導入します。これは不安定な政情のなか、広大になりすぎたローマの領地を治めるために行われた統治方法であり、共同皇帝制を用いて二人のローマ皇帝(東方正帝と西方正帝)が帝国を二分割統治し、そのうえでそれぞれの皇帝がそれぞれの領地を副帝と分割して統治するという四分割統治でした。
ディオクレティアヌス自身は東方正帝に就き、腹心のマクシミアヌスが西方正帝に就きました。帝政ローマでは、皇帝はローマ軍の前線に立って軍を指揮するという伝統がありましたが、広大になりすぎた領土において皇帝自身が軍を率いるというのは難しく、そのため、パクス・ロマーナが崩壊したのちの混乱期において、ローマは外敵の侵入や内乱に上手く対処することができませんでした。しかし、このテトラルキアと呼ばれる四分割統治ではそれぞれの正帝あるいは副帝がそれぞれの領地において直接に軍を指揮することができます。テトラルキアはペルシア軍を破り、またガリアを平定するなどの軍事的な成功を収め、ローマは安定を手にします。
しかし、このテトラルキアによる安定も一時的なものでしかありませんでした。ディオクレティアヌスとマクシミアヌスの両正帝が老齢のため引退すると副帝であったガレリウスとコンスタンティウスが正帝に昇格します。この二人のうち、西方正帝であったコンスタンティウスが死去すると、次なる西方正帝を巡って争いが起きます。東方正帝であったガレリウスは西方副帝であるセウェルスを正帝に昇格させようとしますが、これにコンスタンティウスの息子コンスタンティヌスが異を唱えました。すなわち、今まで通りに副帝が正帝に昇格されるべきという派閥と正帝の息子が正帝の座に就くべきだという派閥に分かれたわけです。さらには初代西方正帝であったマクシミアヌスが正帝に復帰しようとしたり、このマクシミアヌスの息子マクセンティウスも正帝を名乗ったりして、最終的にはセウェルス、コンスタンティヌス、マクシミアヌス、マクセンティウスの四人が西方正帝を名乗る事態にまでなります。
結局、東方正帝ガレリウスとディオクレティアヌスおよびマクシミアヌス両先帝による帝国会議が行われ、ガレリウスの腹心であるリキニウスが西方正帝に、コンスタンティヌスは西方副帝になることになりました。しかしそれでも、争いは終わりませんでした。というのも、かねてから東方副帝であったマクシミヌス・ダイアと、帝国会議の結果、改めて西方副帝になったコンスタンティヌスは、副帝でもなく正帝の子息でもないリキニウスが突然、いわば自らの上司である西方正帝の座に就いたことに反発したのです。やがて四分割されたローマは再び内戦の様相を呈し、最終的には西方副帝であったコンスタンティヌスが勝利し、「唯一の皇帝」を名乗ることになります。のちに「コンスタンティヌス大帝」と呼ばれることになる彼は国力の回復と皇帝による専制政治の確立、ササン朝ペルシアからの攻撃に備えるために、首都を現在のトルコはイスタンブールに位置するビュザンティオンに遷都します。この街は大帝の死後、コンスタンティノープルと改名され、のちの東ローマ帝国(ビザンティン帝国)の首都となります。
(画像:『ディオクレティアヌス胸像』17世紀頃)
【古代ローマの「滅亡」】
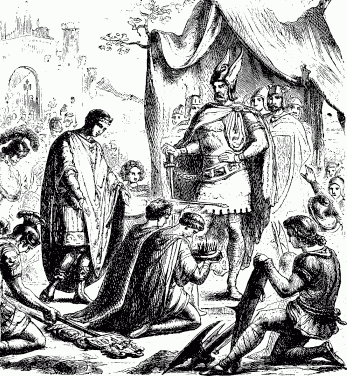 コンスタンティヌス大帝在位の時代にはローマは一時的に安定しますが、彼が崩御すると北方のゲルマン民族がローマ帝国に侵攻するようになり、375年に始まるゲルマン民族の大移動により、ローマ帝国は混乱のなかに突き落とされます。また、コンスタンティヌス大帝崩御後、ローマ帝国は再び分割統治されることになります。394年、東方正帝だったテオドシウスが再びローマ帝国を単独支配しますが、彼がローマ帝国を実質的に単独支配した最後の皇帝となりました。彼の死後、ローマ帝国は彼の息子二人によって分割統治され、「西ローマ帝国」および「東ローマ帝国」へとなっていきます(ただし、当時のローマ市民にとって、ローマはあくまで一つのローマ帝国だったようです)。
コンスタンティヌス大帝在位の時代にはローマは一時的に安定しますが、彼が崩御すると北方のゲルマン民族がローマ帝国に侵攻するようになり、375年に始まるゲルマン民族の大移動により、ローマ帝国は混乱のなかに突き落とされます。また、コンスタンティヌス大帝崩御後、ローマ帝国は再び分割統治されることになります。394年、東方正帝だったテオドシウスが再びローマ帝国を単独支配しますが、彼がローマ帝国を実質的に単独支配した最後の皇帝となりました。彼の死後、ローマ帝国は彼の息子二人によって分割統治され、「西ローマ帝国」および「東ローマ帝国」へとなっていきます(ただし、当時のローマ市民にとって、ローマはあくまで一つのローマ帝国だったようです)。
さて、実質的に「西ローマ帝国」と「東ローマ帝国」に分裂したローマ帝国でしたが、このうち西ローマ帝国は476年、ゲルマン人傭兵隊長オドアケルが西ローマ皇帝ロムルス・アウグストゥルスを廃位したことによって滅亡します。これにより、「古代ローマ」は滅亡したとされます。
この西ローマ帝国の領土の多くはのちにフランク王国によって統治され、このうち、現在のドイツやオーストリア、イタリア北部およびフランス東部にあたるフランク王国領は、800年のカール大帝戴冠とその継承により生まれた中世の神聖ローマ帝国へと引き継がれていきます。
東ローマ帝国はコンスタンティヌス大帝が築いたコンスタンティノープルを首都として、ギリシア的性格を強めながらも(つまり脱ローマ化しつつも)ゲルマン民族の侵入に対処し、1453年、オスマン帝国によって滅亡させられるまで存続しました。
(画像:シャーロット・メアリー・ヤング『ローマ民族史』より『オドアケルに退位させられるロムルス・アウグストゥルス』1878年)