
睡眠中の脳波測定は、異常な波形の誘発以外にも
睡眠自体の評価に用いられています!

睡眠ポリグラフ検査とは、睡眠障害の診断に用いられる検査の1つです!
睡眠障害には、
・不眠症
・過眠症…ナルコプレシー、特発性過眠症
・睡眠随伴症…レム睡眠行動障害、夜尿症
・睡眠運動障害…周期性四肢運動障害、むずむず脚症候群
などがあり、特に近年では無呼吸症候群に代表される睡眠呼吸障害が大きな割合を占めています。
睡眠ポリグラフ検査ではこれらの疾患の病態に合わせて、下に挙げているような記録を組み合わせて行います。
●睡眠段階の記録
・脳波
耳朶を基準とした耳朶基準導出法によって、F3・F4(前頭部)、C3・C4(中心部)、O1・O2(後頭部)を記録します。
睡眠のステージの把握、異常波出現の確認に用いられます。
・顔
脳波に加えて、眼球運動を見るために両目の側に、オトガイ筋の筋電図を記録するためにアゴの両端にそれぞれ電極を装着します。
これらは、レム睡眠の判定に用いられます。レム睡眠は身体の眠りであり、上気道の支持筋や呼吸筋である肋間筋も脱力します。
筋の脱力によって無呼吸が重症化しやすくなるために、眼球運動やオトガイ筋筋電図は判定に必要といえます。
●呼吸の記録
・呼気吸気の把握
呼吸の様子を把握するために、呼気による温度変化を気流として検出するエアーフローセンサ、呼気吸気による圧変化を測定するプレッシャーセンサーなどを鼻に装着します。
さらに胸やお腹にも呼吸による運動を記録するセンサーを巻いて装着します。
・動脈血酸素飽和度
動脈血の赤血球がどのくらい酸素と結合しているのかを調べます。センサは発光部と受光部に分かれ、薬指の爪を挟むようにして装着します。
赤色光と赤外光を透過させ吸光度を測定し、ヘモグロビンと酸素の結合率を算出しています。
・いびきのセンサ
いびきの把握のために首に、気管の音をひろうセンサを装着したり、いびきによる振動を記録するセンサを装着します。
●心電図
心電図は、脳波に混入した心電図を見分けるためや、不整脈の監視のために用います。
とくに無呼吸症候では不整脈との合併が多いため、心電図は症状の評価において重要なものになります。
●四肢筋電図
両足のすねのあたり電極を装着し、前脛骨筋の筋電図を記録します。
これは、周期性四肢運動障害の診断に重要となります。
●体位
無呼吸やいびきは寝ているときの体位に依存することが多いため、体位センサを装着します。特に仰向けになると無呼吸やいびきは重症化します。

↑電極・センサの装着例(※子ども)
脳波はもちろん、目、あごにも電極が装着されています。
また、鼻、胸・お腹、中指にもセンサが着いているのが見えますね!
CC BY-SA 2.5 / File:Pediatric polysomnogram.jpg
アップロード者: / Wikipedia
近年増加傾向にあり、睡眠障害の中でも大きな割合を占める
睡眠呼吸障害についてスポットを当ててみましょう!

●睡眠呼吸障害とは
睡眠呼吸障害とは、睡眠中に呼吸に異常が起こる疾患の総称で、代表的なものは睡眠時無呼吸症候です!
無呼吸とは、一般的に無呼吸が10秒以上続くものとされています。
無呼吸症候群は、無呼吸または低換気が1時間に5回以上起こること、昼間の強い眠気や、集中力の低下などによって定義されます。
無呼吸の原因のほとんどは、上気道が閉塞してしまうことによって起こります。
上気道とは、鼻腔→咽頭→喉頭のことです。気管から肺までは、下気道といいます。
 パブリックドメイン / File:Illu conducting passages日本語.jpg
パブリックドメイン / File:Illu conducting passages日本語.jpg
アップロード者:/ Wikipedia
その閉塞の原因には、肥満、首が短く太い(脂肪が多い)、舌が大きい、あごが小さいなどが挙げられます。
●治療法
無呼吸症候群の治療には、症状にあわせて以下の方法があります。
●生活習慣の改善(症状が軽度な場合)
・睡眠中の体位の工夫(横向き)
・規則正しい生活、運動
・減量
・飲酒の中止
・薬:睡眠薬、点鼻薬(鼻づまりの改善)
●マウスピース(症状が軽度~中等度な場合)
マウスピースを装着することで下あごが少し前方に出た状態で固定されます。
そうすることで、睡眠中に顎が下がって気道を狭めることを防ぐことができます。
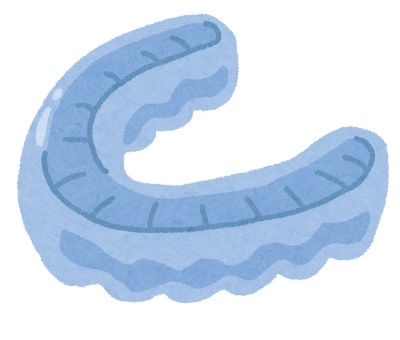
●CPAP(症状が中等度~重度)
CPAPとは、圧をかけてマスクに空気を送り、閉塞した気道を開かせることによって、呼吸ができるようになる装置です。

 パブリックドメイン / File:Full face CPAP mask
パブリックドメイン / File:Full face CPAP mask
アップロード者: / Wikipedia
●手術

上気道に異常がある人に有効です。
口蓋垂(のどちんこ)のあたりを切除し気道を広げます。